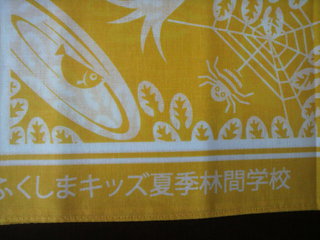2011年09月28日
岩内町長選挙出陣式に行って来ました。
2011年09月27日
東京恵比寿続報
ホテルに着いたのは、24日の午後9時過ぎでした。千歳も羽田も、飛行機も、電車も、家族連や修学 旅行の生徒で、大混雑。・・平時と何ら変わらない東京のエネルギーはどこから来るのか・・移動日となったその日は、移住フェアが終了した職員2名と、軽い軽い反省会。11時過ぎから爆睡をしました。
翌朝、山の手線で、恵比寿駅下車。目的地には、動く道路を使って移動。ガーデンパレスは、予想外に、コンパクトでしたので、すぐ、会場を発見できました。
ブースは、ニセコ町が隣で、後ろが利尻町・・最終日なので、他のブースは販売に熱が・・押し売りモード。 反面、黒松内ブースはさりげなく、試食させ、丁寧な商品説明をし、コンスタントな販売。・・
客の流れが途絶えないので、昼食時間を取らないとのこと。・・外販は、短期勝負なので・・しかたない
なと思いつつ、販売の邪魔しないように、エプロンを置いて、帰路時間を早め、札幌到着したのが五時でした。
3日間の売り上げは、目標の9割近かったとのことです。ネット販売等が一般化していますが、直接街 頭販売は、買い手と売り手、双方の心が通い合う、商いの原点です。東京だから、食の安全性に敏感 だし、プロモーションの仕方、生活文化のトレンドも参考になります。 担当外の職員を研修として、派 遣したい・・・・政策の中央要請行動では、浮かばない・・・そんな気持ちにさせてくれた東京でした。
関係職員、サッポロビール関係者の皆さん、ご苦労様でした。
2011年09月24日
23日から東京恵比寿で特産品をPRしてます。
23日からの3連休、東京恵比寿ガーデンプレイスの特設会場ブースで、サッポロビール北海道本社主催の北海道はうまい・・北の大地の収穫祭・・・が行われています。
代表33市町村の一つとして、黒松内町からトァヴェールが、ハムの新製品を持参し、初参加。施設長と開発担当者の応援のため、佐藤副町長が、昨日から東京入りし、今日は、二時から、移住フェアで上京中の企画担当者二名と町の紹介・自慢をすることになっています。
私は、今日24日から、上京し、最後の1日を激励。特産品の屋外PR・・・17年振りだなあ。
黒松内町に縁のある都民の皆さん、顔出してください。お待ちしております。
写真は、23日のブースの様子です。

熱郛神社宵宮祭と協賛芸能発表会
22日の午後6時から、白井川地区の熱郛神社の宵宮祭。四月に採用になった2名の職員を含む4人で、参詣・参拝をさせていただきました。
熱郛神社は、白井川稲荷、角十、赤井川、共心、大谷地などの神社を大正10年に統合し、大正13年に現在位置に建立されたそうです。 戦前の村社の歴史があることから、神社御輿、猿田彦、宮司さんも3人と、祭事も、厳粛・荘厳なものです。
各地区の氏子役員、団体代表等、40名近くの皆さんとともに、玉串を奉てんし、二日間に渡る祭りの成功と、豊年満作、地域の発展を祈ってきました。
御神酒をいただいた後は、会場を移して、芸能カラオケもちまき大会。
小中学生の・・よさこいソーランが始まると、たくさんのおひねりの嵐、白井川でしか見られない、地域の絆の深さ、一体感に、あらためて幸せな気持ちにさせていただきました。ありがとうございました。
2011年09月22日
愛媛県立野村高校の酪農実習生・・ようこそ
22日、愛媛県立野村高校畜産科2年生16名から構成される酪農実習班の歓迎受入式が、役場会議室で行われました。
台風15号で、来町が心配されましたが、全員、 空路・陸路を乗り継いだ10時間の長旅。それにもめげす、元気はつらつと、研修の抱負を述べてくれました。
野村高校の生徒の受け入れは、旧野村町と本町がブナ林を縁とした姉妹提携(平成3年締結)の交流事業の一つで、現西予市との姉妹市町提携が結ばれた以降も、継承されている教育交流です。
生徒の皆さんは、それぞれ、添別、大成、西沢、大谷地、北作開の受入酪農家の皆さんに九日間お世話になります。 酪農という土と草と牛と人の営みに、たくさん、生徒を育てる力・・教育力があるからこそ、学校は、この特色ある研修を継続していると思います。
農畜産物の生産はもとより、環境、教育、文化など、その地域の自然と人の営みによって、育まれてきた農業・農村の多面的な力、それらを、一つだけ抜き出して、そっくり輸入することできません。
TPP、規模拡大によってもたらされるであろう副作用によって、我が国は大切な宝物を失おうとしています。
今後の農政の動向をしっかり、見極め、地に足の着いた地域農政を展開していきたいものです。

2011年09月21日
台風15号に備えて・・・
15号が北上しています。防災担当の総務課では、インターネット等で、刻々変化する台風情報等から、災害緊急体制をシュミレーションしていますが、消防が24時間体制で、朱太川増水監視を行い、1時間30ミリ以上で、3時間、50ミリ以上、24時間で80ミリ以上で被害予想される場合、町職員が緊急招集されて、管理道路、普通河川、農地冠水、住宅浸水などのl現場調査の確認を行います。
12号台風で冠水した町道や病院の裏手の敷地について、排水ポンプの作動準備は完了しております。
氾濫危険水位を超えた場合、防災無線を通して、避難勧告及び指示を発令することがあります。
情報に留意してください。
○原発安全対策等の要望について
後志町村会として、知事、北電、経済産業省道事務所等に、9時から要望活動を行っています。
副町長が、代理で出席しました。
敬老会・・ご苦労様でした。
今日、11時から町民センターで敬老会が行われました。
65才以上の高齢者は、1050人を超え、3人に1人が65才以上ですが、敬老会のご案内は、75才以上の皆さん。今年の対象者は、646人でしたが、当日は、270人の方が、出席しています。
町を代表して、88才、95才、100才の皆さんに、敬老祝い金を贈呈させていただきました。
町で最高齢は、老人ホームに入所されている鈴木シズエさん、103才。男性は、赤井川の斉藤卓二さん、98才です。長年に渡って、仕事に励み、養育や若い世代のご指導をされ、家庭や地域を支えていただきました。
開会のあいさつでは、会場にお越しいただけなかった皆さんも含めて、今後ともご壮健で、町の発展を見守りいただくよう期待と、感謝を申し上げました。・・・斉藤裕さんの軽妙な司会による芸能発表が始まると、会場は、一気に高揚、あっという間の二時間が過ぎ、参加者は、来年の再会を誓いあいながら、会場を後にしました。開催準備いただいたスタッフ、女性会、日赤奉仕団、各施設の職員の皆さん、ご苦労様でした。

陸自函館駐屯地中隊長さんと防衛白書
ブナの里振興公社パークゴルフ大会
19日、前日とうって変わって日差しが差し込む歌才パークゴルフ場に、町内外から74名の腕自慢プレイヤーが集結しました。
公社は、自然の家をはじめ3つの交流施設を管理運営する町が51パーセント出資する株式会社。
本来事業の他に、音楽鑑賞やスポーツ分野などの自主企画事業を展開しています。
本大会は、お客様の還元事業としてスタートしましたが、競技レベルは年々高く、商品も豪華なメジャー 大会に成長して いるようです。
会場でいただいた名簿を見たら、参加することになっていましたが、何かの間違い・・すかさずキャン セルし、激励のあいさつして、早々に失礼いたしました。 2日間、天候に恵まれ、良かったと思います。
2011年09月20日
味の園遊会
17日、緑ヶ丘老人ホームで、味の園遊会のお誘いがあり、出席してきました。
あいにくの雨模様で、中庭から食堂での開催に・・・・
前日の議会終了の後の、激励懇親会で飲み過ぎたせいか、下降気味の体調でしたが、職員の皆さん の手作りおでんと、芸能発表に刺激されて、元気回復。愛燦々を披露してきました。
それにしても、湯の里まつり、味の園遊会、二度とも雨。雨男は誰でしょう。
連休・グリーン上のスポーツ全開です。
三連休の真ん中、18日に、歌才森林公園を会場に、家族連れ160人が参加し、みんなでクロスカントリー大会が開催されました。前日とうって変わって、10月上旬の気温、開会式後、まもなく、雨で、プログラムも繰り上げ進行。 それでも、事故も無く、自然の家での豚汁昼食と、お楽しみ抽選会で、盛り上がったそうです。(来賓案内受けましたが失礼しました。)
同日には、蘭越町のゴルフ場を会場に、20代から70代の愛好者37名が参加し第一回黒松内町・町民ゴルフ大会が開催されました。
主催は、同大会実行委員会で、黒松内町、体育協会、商工会等12団体が協賛、ゴルフは2016年からオリンピック種目に復活するスポーツですが、本町においても、この大会を契機に、市民権を得ることと思います。ちなみに、記念すべき優勝とベスグロは、キャリアとコースを知り尽くし、巧みな技を駆使し、運を味方にした、ベテランプレイヤーお二人で、頭文字がいずれもS。
表彰式・反省会では、ミスプレイ反省の弁や、来年の開催に向けたプランも語られ、参加者相互の親睦も深まった有意義な1日でした。 仕事の傍ら、大会の企画・運営に携わった、実行委員会の役員・事務局の皆さんご苦労さんでした。
2011年09月15日
酪農ヘルパー組合後藤会長さんが来庁しました。
搾乳前の忙しいところ、酪農ヘルパー組合の後藤会長さんが、用事を済ませた後、立ち寄っていただきしまた。短い時間でしたが、先日、サッポロで行われた草地協会のフォーラムの話しをきっかけに、酪農の奥深さの話しに、花が咲きました。
今日の一般質問は、福本議員。肉牛のブランド化、地産地消の推進のための町の支援策強化や、酪農家の所得向上の一策として増頭期待も高いことから、育成舎や乾乳舎の整備支援の有効性について、意見が交わされました。 牛の成長ステージに応じた適正な飼養管理は大切です。
ニーズ調査をした上で、簡易な方法で整備することであれば、前向きな支援検討をしたい答弁いたしました。
今、酪農においては、自給飼料の有効活用が課題で、牛の給食センターと言われるTMRと放牧の二極化が進んでいます。アメリカ型とニュージーランド型という分類は、必ずしも正しくはありませんが、黒松内は、黒松内型の放牧と舎飼の融合が、低コスト、持続可能な酪農になるような気がしますが、堆肥センターも含めて、循環と最適コストを基本にすると、答えは整理されるような気がします。
明日は現職議員の皆さんにとって、最後の定例会で最終日、建設的議論が深まることを期待します。
2011年09月14日
札幌ビール・今井部長さんが来庁しました。
12日から、九月定例議会が開会していますが、明日から一般質問です。
奥の深い農業問題を中心に、各課長と答弁内容の最後の打ち合わせをしておりますが、その合間をぬって、札幌ビールの今井部長さんが、7月に札幌大通公園で開催されたビアガーデンのイベントへの参加のお礼と、事業報告のため、わざわざ、訪ねていただきました。
当日は、ビーフ天国のPRをかねて、実行委員会の役員数名の皆さんと、産業課・トァヴェールの職員の皆さんが、町のピーアールをしたそうです。
クラシック定番のおつまみに、黒松内バニラアイスも紹介され、販売も好調だったとか。
ご配慮に感謝です。
サッポロビールさんには、一昨年から、ブナ林の再生プロジェクトを支援していただいて以来、コラボが進んでいます。その一環として、9月23日から25日、東京恵比寿ガーデンパレスでの北海道フェスに、ハムの新作を持参して、トァヴェールの職員等が、乗り込みます。
前半には、移住関係のフェスも隣のブースであり、企画から二名の職員が参加、私と副町長も、手分け して激励に行く予定です。
今日は東京34度・・・上京の頃には、涼しくなってくれることを祈ってます。

2011年09月13日
歌才神社のお祭りに参詣・参拝してきました。
13日午後1時から、歌才神社のお祭りでした。
歌才は、ブナ林や湿原で、国内はもとより、国際的にも、その道の研究者の間では、知れ渡っている地名です。
平成9年、朽ち果てていた社を、地域皆さんの熱意と浄財により、再建立されています。
お祭りと、新年の参拝に、年に、二回、地域の人たちが顔を合わせる、地域の守り神、結束のシンボル です。
宮司さんにより一連の儀式が終わり、その後、ちょっとした親睦会が行われます。
毎年、ふるまわれるのが、地域で栽培されている新ソバ。落合さんが堆肥をたくさん入れた畑で採れ た信州系のとても美味しいソバです。
今、なだらかで起伏のある落合さんのソバ畑は、道内でも、ビュースポットとして、雑誌に紹介される など、黒松内の代表的農村風景の一つになってきました。
高齢化が進み、冬場の屋根の除雪に苦労していること、福祉バスがありがたいこと、年金で介護施 設に入れれば・・・等、地域ならではの願いが出されました。
防災無線については、二回放送して欲しい。温泉休館の放送は良かった。何よりも、お悔やみ情報 が必要だね。等々、様々な意見がありますが、ある意味、地域と役場を結んでいるようです。
稲作づくりに挑戦した開拓者は、高層湿原であったため、用水を確保できず、断念。
極小規模の酪農と畑作で、生計を立ててきましたが、今は、ソバ畑と、湿原の里として、注目されはじめています。
つい3日前、東ロンドン大学と東京大学から、著名な先生が、この地に踏査に来たことを、何故か、言 い出せないまま、帰ってきました。 豊穣の秋が訪れるますように、神様お願いします。

2011年09月12日
ふくしまキッズ夏季林間学校からお礼の手紙
最大500名を越える福島のこども達が約1ヶ月、北海道各地で、夏休みを過ごしました。
このほど、主催にあたった福島の子どもを守ろう実行委員会の進士委員長から、自然学校や、自然の 家に宿泊 し、40名近い子ども達が、野原を駆けめぐり、友と遊び、地域の心温まる歓迎を受けて、 満面と笑顔と元気がよみがえったことへの感謝、さらには、子ども達が大人になった時、今回の体験 を通し、心ある福島県、明るい日本を創るよう成長して欲しいという願が込められたお手紙をいただきま した 。
つらいだろうけど、危険を回避して、とにかく、元気に育って欲しい。大人になったら、このような 心配 が二度と起こらない社会をつくる担い手になって欲しい。来年も待ってる。とういう趣旨のあいさつをさせていただきましたが、中学1年生の代表の女の子から、幸せの黄色いハンカチをいただいて、胸が詰ったことを、今、思い出しています。活動内容が紹介されているホームページ。参考まで。
2011年09月09日
自民党移動政調会と原子力発電について
8日、午後から倶知安の第一会館で開催された平成24年度の予算関連を中心にした自民党移動政調会に参加。宮内蘭越町長から新幹線、高速道路等の整備推進について、要請した後、各町村長から個別地域課題について、要請をしました。
円高で、外国資本による事業計画の停滞や、外国人観光客の減少対策、日本海の磯焼け対策、原子力災害避難経路の整備等、要請は多岐に渡りましたが、原発の危険性や不安をあおる報道に義憤を感ずる、泊発電所は安全だという意見が出た一方、事故が今だに収束せず、被害が拡大している中で、原発事故は、決して、起きてはならないこと、原子力安全委員会等、国の責任、さらには子々孫々に負の遺産を残さないため、過渡期のエネルギーとして認識し、エネルギー政策を抜本的に見直すぺきという意見も出されました。
福島原発の事故とその後の放射能拡散は、46億年の地球の生物の進化と多様性の健全性を大きく損なうという、地球規模の人災であり、畏敬すべき自然界への冒涜となりました。
この結果は、かならず、未来の人類に、牙をむき、悲しい結果をもたらすことが確実視されています。
私は、腹を切って、責任が取れる事象であれば、そこまでの覚悟と、認めるかもしれませんが、原発事故は、時の政治家も、官僚も、学者も、まして、一自治体の首長が、責任をとれるものではないということが証明されました。このような、まったく、人知の及ばない領域の問題について、知事や首長に、あたかも判断できるような幻想を与え、発言権を付与すること自体が、間違っています。
私も、一応、科学技術の一部をかじってきましたが自然界のことは、私たちは、解っていないことの方が、圧倒的に多いのです。 地球は生命体、ガイアであることを、改めて認識すると、何がだめなのか・・が見えると思うのですが・・・これからも、原子力発電については、私見を述べていきたいと思います。
事故が収束しない
2011年09月08日
朱太川が増水
台風12号くずれと13号の気圧の谷で、5日の夕方から6日の午前中にかけて、黒松内町に大雨・洪水・雷警報が出されました。
1日からの累計で、降水量は、190ミリ、6日の十時頃には、朱太川も、通常水位より1メートル90センチ近く上昇し、さらに、50センチ増加すれば、作開地区に避難勧告かとも思いきや・・・幸い、雨は小降りとなり、事なきを得ました。
9時から、災害対策本部に準じて、臨時課長会議を招集、冠水等の被害調査を行いましたが、中流、下流域で水門管理の遅れからの逆流、一部河川敷地に隣接している畑の冠水等の被害はありましたが、、直接的な家屋の床下浸水などはありませんでした。
今年も、ゲリラ豪雨は、多発しそうです。普段から防災マップなどを活用し、防災対応力の向上に努めていただきたいと思います。尚、8日、道主催の第二回防災計画見直し有識者検討会議、本町からも職員が傍聴に参加しています。

2011年09月06日
地域主権民主党政策懇談会
5日、余市町の水明閣を会場に、民主党道議会議員の皆さんと町村長が、地域が抱える諸課題と道が果たす役割、平成24年度国や道の予算編成についての要望等について、意見交換しました。
黒松内町からは、現在進められている朱太川の治水工事に、引堤や氾濫原の確保など、生物多様性保全を取り入れた工法の導入や、堆肥センターの改修事業に対する国の補助制度の硬直性に対する疑問等、7項目を中心に要望しました。
道政については、原発事故を受けて、ダイナミックにチェンジする好機、経済成長優先主義から脱皮し 循環や生物の多様性等をキーワードにした、道政ビジョン策定を急ぐべし、それによって、エネルギー や農政、土木行政等、多様な分野で劇的な構造転換が行われると私見を述べさせていただきました。
日本の政治風土は、島国文化を引きづり、国地方問わず、政策よりも、政治キャリアと政局が優先さ れる特異な体質です。過去に学び、未来への責任を果たす。国や地域を憂う。これは保守本流の首長 の本懐ではないでしょうか。・・・ふと、そんなことを想うこの頃でした。
北海道女子軟式野球大会・豊幌神社の宵宮祭
3日から4日にかけて、北海道女子野球大会がブナスタジアムで、開催されました。雨で中断する中、4チームのリーグ戦、男子顔負けのきびきびしたプレイ、レベルの高さに脱帽。優勝は、苫小牧チーム。傘をさしての観戦でしたが、地元ファンの皆さん、関係者の皆さん、ご苦労様てせした。
4日の夕方、豊幌神社の宵宮祭、参詣・参拝してきました。
神社総代を区長さんが兼ねていますが、限界集落化が進み、いつまで神社を守れるか・・不安の声が聞こえました。神酒の効用か、即席行政懇談会が始まり・・景観条例への疑問や、町道の橋の段差解消等、要望も寄せられましたが、祭りは、数少ない地域結束を図る行事です。
祭りが続く、集落づくりの強化に努めたいと思うこの頃です。
陸自函館駐屯地創立61周年で熱中症寸前
4日、陸上自衛隊函館駐屯地創立61周年記念式典に参加してきました。
七時半に、家を出で、会場に着いたのは、9時半。一般開放された駐屯地は、出店もあり、会場は一般家族連れで大にぎわい。
あいさつは、無かったものの、道南の市・町長さんらの1人として、紹介を受けました。
七部隊の観閲・行進は、勇壮・厳粛。
渡島半島の防衛・地域の安全安心・災害の復旧支援に、身を挺して活動する自衛隊の皆さん
に、心から感謝と敬意を寄せるものであります。
それにしても、雨上がりの、青空は、暑かったあ。・・・・
来年8月国際花粉学会のエクスカーションが黒松内で。
湯の里まつりを後にして、昨年、生物の多様性シンポで訪れた中央大学の西田先生、道教育大紀藤先生など一行4名と執務室で懇談いたしました。
来年の8月に、東京で、国際花粉学会が行われ、エクスカーションの一部に、歌才ブナ林が組み入れられることになり、1泊二日の日程で、諸外国20名の先生が来町します。
今年の9月には、イギリスから、湿原分野の先生も来町し、黒松内の豊かな自然を踏査することになっています。ホットスポットとして、グローバルかつローカルなバランス感覚を失わないように、町の役割を果たして行きたいと思います。
湯の里まつり・・雨で職員の皆さん・・ご苦労さんでした。
北海道の未来の草づくり フォーラム・・熱かった。
防災訓練を後に、列車で札幌イン。2日から、草地協会主催の北海道の未来の草づくりを語るフォーラ ムに賛加。9時半から交流会含めて、三友、石橋、山田、諸先生先生はじめ、名だたる実践家13名の 思いを伺い、感心゜・感動の1日でした。循環・土や草・牛を信じること。三友先生の言葉が脳裏に焼き 付きました。演出していただいた樫野さん、キャストの皆さんに感謝します。

2011年09月01日
防災訓練お疲れさまでした。
9.1の防災の日、震度4を想定して、全町防災訓練が行われました。 今年の訓練は、自衛隊の協力をいただいて、炊き出しや、ヘリコプターの降下による救出体験、装甲車避難体験などが行われました。
3.11以降、日本列島の地殻変動期を迎えていると言われています。黒松内活断層を抱え、福祉施設利用者の多い黒松内町は、災害弱者も多く、個人、地域、町全体としての日頃の防災に対する備えが、管内でも最も必要な地域の一つです。
町としても、訓練上の課題把握や、原子力など新しい災害を想定し、国や道の方針と調整を図りながら、防災計画の見直しや、訓練内容の見直し、安全・安心な防災行政の充実に努めていきたいと考えておりますので、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
残暑厳しい中、参加された1070名の町民の皆さん、関係機関や支援企業の皆さん、お疲れさまでした。




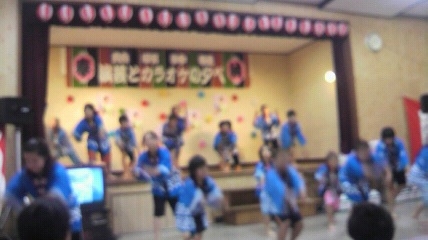

![IMG_5707[1].jpg](http://kuromatsunai.com/officialblog/IMG_5707%5B1%5D-thumb.jpg)